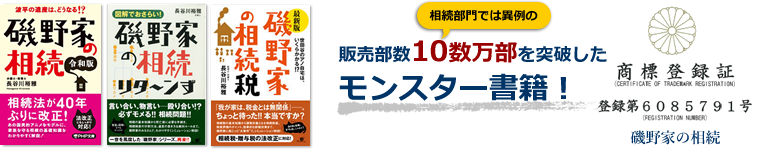カテゴリー:『 知識の解説 』の記事一覧
- おなかの中に被相続人の子がいる場合 -遺産分割の問題 おなかの中に被相続人の子がいる場合遺産分割の問題 胎児は生まれた者とみなして相続人になることができます。 相続開始時にまだ出生していなくても、出生したら相続人として遺産分割に参加することができます。もっとも胎児は死産の可能性もあり、遺産分割協議に現実には参加できない可能性もありますので、相続人に胎児がいる場合は、実際に生まれてから遺産分割協議をするのが無難です。 なお遺産分割にあた…
- その他の財産の相続 -遺産分割後の手続き その他の財産の相続遺産分割後の手続き その他に相続について名義書換えが必要なものとしては、自動車、船舶等が考えられます。いずれの場合でも一般的に名義変更手続に必要な書類は、相続があったこと、相続人の範囲、特定の相続人に当該相続財産を帰属させることについての他の相続人の同意があったことを証明する書類が必要となります。 一般的に必要とされる書類 …
- ゴルフ会員権の相続 -遺産分割後の手続き ゴルフ会員権の相続遺産分割後の手続き ゴルフ会員権には、(1)社団法人制のゴルフクラブの会員権、(2)株主会員制のゴルフクラブの会員権、(3)預託金会員制のゴルフクラブの会員権、の3種類があります。ゴルフ会員権の相続の可否はゴルフクラブや種類によって異なります。会則の中に「会員が死亡したときはその資格を失う」旨の規定があるゴルフクラブの会員権は、相続の対象にはなりません。ゴルフクラ…
- 不動産の相続 -遺産分割後の手続き 不動産の相続遺産分割後の手続き 遺産分割で不動産を相続した場合、必ず相続登記を行う必要があります。不動産には登記制度があり、登記が対抗要件とされています。対抗要件とは、第三者に対して、当該不動産が自分のものであることが主張できる要件であり、つまり、不動産を取得しても不動産登記を済ませておかないと、不動産の所有を有効に主張できないということです。遺産分割は相続人の遺産分割協議によって…
- 代償分割 -遺産分割の方法 代償分割遺産分割の方法 代償分割とは、現物取得することにより相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、その他の相続人に対して、金銭を支払うなどして過不足を調整するという分割の方法です。例えば、遺産が住居用の不動産のみで、そこに相続人のうちのある者が生活しており、その者の生活関係の安定を考慮しなければならない場合や、農地、営業用資産など、細分化を避ける必要性が高い場合、相続財産の種類…
- 具体的な調査方法 具体的な調査方法相続財産の確定 不動産 預貯金等 株式・有価証券 生命保険契約等 不動産 相続財産の中で不動産は大きな割合を占めることが多いようです。不動産は共同相続人間で分けることが難しく、分割で価値が下がることもあるので、相続争いの中心課題になることも多いといわれます。まず…
- 具体的相続分 -相続人・相続分の確定 具体的相続分相続人・相続分の確定 指定相続分や法定相続分によって、相続財産に対する各共同相続人の具体的な相続分が最終的に確定されるわけではありません。協議分割においては相続人全員の合意があれば、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決めることができます。また、相続財産に対する共同相続人の相続分を具体的に確定するにあたって、相続開始時に現存する財産の価格を基礎で計算した場合に…
- 協議による分割(遺産分割協議) -遺産分割の方法 遺産分割協議による分割(遺産分割協議)遺産分割の方法 協議による分割(遺産分割協議)とは、共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続です。共同相続人全員の話し合いでどのように分割しても構いませんので、法定相続分と違う分割をしてももちろん問題ありません。遺言がない場合、遺産分割の内容は共同相続人の自由に任されていますので、特定の相続人の取得分をゼロとするような遺産分割協議も有効です…
- 単純承認 -相続の放棄と承認 単純承認相続の放棄と承認 限定承認や相続放棄をしないで、相続人が被相続人の財産を無条件で相続することを単純承認といいます。単純承認には限定承認や相続放棄のような特別の法的手続きは必要ありません。相続開始から3か月が経過することで当然に相続を承認したことになります。 法定単純承認 相続放棄や限定承認をしようと思っても、相続開始から3か月以内にそ…
- 取得した遺産に問題があった場合 -遺産分割の問題 取得した遺産に問題があった場合遺産分割の問題 遺産分割の結果、手にした相続財産に何らかの瑕疵がある場合があります。 相続財産の瑕疵とは、相続人が取得した財産が他人の物だったり、当初の話と比べて数量不足や一部滅失があったり、土地に地役権や用益権、担保権などの制約があったり、遺産である債権の債務者が無資力で債権回収が困難であったりするなどをいい、分割協議の時点では判明していなかった不都…
- 外国に住んでいる相続人がいる場合 -遺産分割の問題 外国に住んでいる相続人がいる場合遺産分割の問題 相続人の中に海外に住んでいる者がいる場合、遺産分割協議への参加が困難になります。この場合は家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てて、財産管理人を代理人として遺産分割協議を行うことができます。ただし、この代理人には共同相続人が就任することはできません。 また本人が遺産分割に参加できるとしても、実際に遺産分割協議書を作成の際には、署名、…
- 寄与分 -相続人・相続分の確定 寄与分相続人・相続分の確定 寄与分と寄与分計算 寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持または増加に特別の寄与貢献をした相続人に与えられるものです。寄与分は遺産分割の対象である相続財産には含まれないので、寄与分がある場合は、相続財産の中から寄与分を別個に切り離して、残りの財産を分割して相続することになります。寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に加えて、寄与分を受…
- 換価分割 -遺産分割の方法 換価分割遺産分割の方法 換価分割とは、遺産を金銭に換価して、その代金を共同相続人で分割する方法です。現物分割が不可能な場合や現物分割では著しく遺産の価値を下げてしまう場合などに行われます。例えば、2筆の土地上にまたがって建物がたっているような場合、土地を1筆ずつ現物分割してしまうと価値を損なってしまいます。また代償分割を行なうにも、相続人に債務負担能力がない場合等も換価分割を利用し…
- 株式・有価証券の相続 -遺産分割後の手続き 株式・有価証券の相続遺産分割後の手続き 相続によって株式を取得した場合は、株主名簿の名義書換手続を行わなければ、相続人は株主であることを会社に対抗できず、株主としての議決権行使や配当請求に際して支障が生じることになります。そのために、相続した株式について株主名簿の名義書換えを請求する必要があります。なお、株式が譲渡制限株式であっても、相続等の包括承継の場合には譲渡制限の規定の適用は…
- 法定相続について -よくある質問 遺産分割Q&A 法定相続についてよくある質問 遺言Q&A 相続とは何ですか? ある人(被相続人)が死亡した時に、「死亡」という事実を理由として、その人の財産に属した権利義務や地位を法律で定められた人(法定相続人)が承継することをいいます。 いつ相続が開始しますか? 被相続人の死亡と同時に相続が開始します。 誰が相続人になりますか? 誰が相続人になるかは民法で…
- 法定相続人 -相続人・相続分の確定 法定相続人相続人・相続分の確定 被相続人の財産を相続できる可能性のある関係者は、(1)配偶者、(2)子(代襲相続人である孫・曾孫を含む)、(3)父母(祖父母)、(4)兄弟姉妹(甥姪)などです。そのうち誰が当該相続の相続人になるか、その相続人の中で誰がどの程度の優先権があるかについては、民法で規定されています。これを法定相続人といいます。また、法定相続人であっても、自らの意思で相続人…
- 法定相続分 -相続人・相続分の確定 法定相続分相続人・相続分の確定 法定相続分 法定相続人法定相続分備考 配偶者 子配偶者1/2子が数人ある場合は、相続分は均分 子1/2 配偶者 父母配偶者2/3父母が数人ある場合は、 相続分は均分 父 母1/3 配偶者 兄弟姉妹配偶者3/4兄弟姉妹が数人ある場合は、相続分は均分 半血兄弟…
- 熟慮期間の伸長 -相続の放棄と承認 熟慮期間の伸長相続の放棄と承認 相続放棄も限定承認も、自己のために相続の開始があったこと知ったときから3か月以内(熟慮期間)に行わなくてはなりません。しかしながら被相続人の財産や負債の額が明らかではなく、相続放棄をするか限定承認をするか決定できず、3か月以内に調査を完了し、判断する時間が足りない場合など理由がある場合は、この期間を延長する申立てを行うことができます。 …
- 特別受益 -相続人・相続分の確定 特別受益相続人・相続分の確定 特別受益と持戻し計算 被相続人の死亡後は共同相続人間で法定相続分に従って遺産を相続するのが原則です。ところが、共同相続人のうちで、被相続人から遺贈や結婚の際の持参金をもらったり、婚姻、養子縁組または生計のための贈与を受けた者がある場合は、それら贈与をまったく何らの考慮もせずに法定相続分に応じてさらにそれらの者に遺産を取得させるこ…
- 特別受益、寄与分について -よくある質問 遺産分割Q&A 相続分に影響するもの(特別受益・寄与分)よくある質問 遺言Q&A 特別受益者とは何ですか? 特別受益者とは、被相続人から遺贈を受けたり、相続開始前に被相続人から結婚、大学入学などの際に贈与を受けたりして、特別に受益を得た相続人のことです。 特別受益にあたる贈与とはどのようなものですか? 生前贈与については、持参金、新居、道具類、高額の結納、高額の新婚旅行費用…
- 現物分割 -遺産分割の方法 現物分割遺産分割の方法 現物分割とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法です。例えば、「甲にはA土地を、乙にはB土地を、丙にはC土地を取得させる。」というように、それぞれの財産を、その形態を変えることなくそのまま各共同相続人に配分する方法です。遺産の分割とは、相続財産全体に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きですから、それぞれの財産について、その取得者を別…
- 相続人がいない場合 -遺産分割の問題 相続人がいない場合遺産分割の問題 相続人が存在しないといわれる状況には、戸籍を調査した上で相続人が存在しない場合と、戸籍上は相続人が存在するが相続の放棄、相続欠格、相続廃除によって相続人がいない場合とが考えられます。いずれの場合でも、相続人がいないからといって法的手当を講じず、そのままにしておくと、相続財産は所有者がないまま宙に浮いた状態となってしまいますので、当該相続財産を相…
- 相続人が確定したら -相続人・相続分の確定 相続人が確定したら相続人・相続分の確定 相続人が確定したら、被相続人を中心とした相続関係図を作成し、相続人リストを作ります。相続関係図は被相続人や相続人などの戸籍謄本、相続人リストは住民票をもとに正確に作成します。 相続関係図(相続関係図、相続人リスト含む)…
- 相続人でない人が加わった遺産分割 -遺産分割の問題 相続人でない人が加わった遺産分割遺産分割の問題 遺産分割は、共同相続人全員が参加し、全員の合意で成立することが必要です。そこに相続人でない者が加わった場合は無効と解され、原則として当該遺産分割は無効とし、やり直すことができます。相続人でない者を加えて遺産分割協議がなされる場合というのは、そもそも遺産分割当時から相続人ではない者(表見相続人など)が相続人として分割協議に加わっている場…
- 相続人の中に未成年者がいる場合 -遺産分割の問題 相続人の中に未成年者がいる場合遺産分割の問題 法律行為一般において、未成年の行う法律行為は親権者の同意が必要とされています。 遺産分割協議も法定代理人の同意が必要な行為ですが、未成年者もその親権者も相続人となる場合、親子が同じ被相続人の遺産を分け合うという点で、客観的にみて利害が対立しているといえます。この関係を利益相反といいます。 また、親権者が共同相続人である数人の子を代理して…
- 相続人の調査 -相続人・相続分の確定 相続人の調査相続人・相続分の確定 1 調査すべき情報 (1)被相続人の身分関係に関する事項 まず、被相続人の死亡年月日および最後の住所地を知る必要があります。最後の住所地は、相続放棄や限定承認などの家事審判を申述する場合に、管轄裁判所を判断するために必要となります。死亡年月日は相続開始年月日となり、相続放棄・限定承認の申述時期を判断する場合などに必要となります。また…
- 相続人の1人が行方不明の場合 -遺産分割の問題 相続人の1人が行方不明の場合遺産分割の問題 相続人のうちの1人が行方不明であるからといって、当該相続人を無視した遺産分割協議を行うことはできません。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となりますので、ある相続人が行方不明だと相続手続を進めることができないということになります。相続人が行方不明の場合の手続は行方不明の態様により、2つの方法があります。 生きているこ…
- 相続人の1人を除外して遺産分割を行った場合 -遺産分割の問題 相続人の1人を除外して遺産分割を行った場合遺産分割の問題 遺産分割は、共同相続人全員が参加し、全員の合意で成立させることが必要です。明文の規定はありませんが、一部相続人の参加しない遺産分割協議は無効と解され、相続人の1人を除外して遺産分割を行った場合、原則として当該遺産分割は無効としてやり直すことができる、とされています。 遺産分割当時にすでに存在していた相続人を除…
- 相続人以外の関係者 -相続人・相続分の確定 相続人以外の関係者相続人・相続分の確定 遺産分割は共同相続人によって成立するものですが、ケースによっては遺産分割に相続人以外の者が参加する場合があります。 住所が不明で連絡がつかない相続人がいる場合 この場合は不在者のために財産管理人を置き、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。手続きとしては、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が財産管理人を選任し…
- 相続廃除について -よくある質問 遺産分割Q&A 相続権を失う場合(相続欠格と相続廃除)よくある質問 遺言Q&A 相続権がなくなる場合とはどのような場合ですか? 相続放棄、相続廃除がなされた場合や相続欠格に該当する場合です。 相続欠格とは何ですか? 相続欠格とは、相続に関する不当・不正な行為をした相続人の資格を法的にはく奪する制度です。はく奪という強い効果が働きますので、その事由(欠格事由)は法律で決まって…
- 相続放棄 -相続の放棄と承認 相続放棄相続の放棄と承認 相続放棄とは、被相続人の一切の財産を相続することを放棄することをいいます。相続放棄は、相続の開始によって相続人に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示を意味します。つまり、相続放棄によって初めから相続人ではなかったことになります。なお、相続放棄は生前にはできません。例えば生前に相続放棄をしていても、相続開始後(被相続人が亡くなった後)…
- 相続財産を把握する -相続財産の確定 相続財産を把握する相続財産の確定 まず、被相続人の財産について整理し、財産リストを作成しましょう。財産リストを作成し、被相続人がどんな財産を持っているかが明らかになれば、どのように相続財産を分割するか明確に話し合うことができます。相続財産には預貯金、不動産、株券、装飾品などさまざまなものが考えられます。これらの財産について、例えば預貯金がどこの金融機関にどれだけあるか、どこにある不…
- 相続資格の確定 -相続人・相続分の確定 相続資格の確定相続人・相続分の確定 法定相続人が当然に相続をするとは限りません。相続人には自ら相続を辞退する権利もありますし、ある一定の条件で相続権をはく奪される場合もあるからです。よって、法定相続人が相続の意思があるかどうか、相続資格があるかどうかを確認することも重要なポイントとなります。 相続欠格 相続欠格とは、相続に関する不当・不正…
- 知らない相続人が出てきた場合 -遺産分割の問題 知らない相続人が出てきた場合遺産分割の問題 相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。そこで、遺産分割協議を行う前に、必ず相続人を正確に確定する必要があります。被相続人の身分関係を調査することで、実は被相続人が過去に養子縁組を行っていたり、前配偶者との間に子をもうけていたり、認知している子供がいたり、などが判明する場合があります。知らない相続人の出現の可能性は十分あります…
- 知識の解説 遺産分割トラブルのポイントや遺産分割に関する法律用語の解説を紹介しています。 相続人・相続分の確定 遺産分割において初めにすることが相続人の確定です。これによって相続分の確定もできます。 相続人の調査 法定相続人 相続資格の確定…
- 認知された子が現れた場合 -遺産分割の問題 認知された子が現れた場合遺産分割の問題 認知とは、父または母がその婚姻外の子を自分の子と認めて法律上親子関係を生じさせる行為をいいます。認知は、認知者の生前行為として届出で行うことができますが、遺言によってもできます。成年に達した子を認知する場合は本人の承諾、胎児の場合は母親の承諾が必要です。また、子(被認知者)から親に対して、認知を求める訴えを起こすこともできます。父親の死亡後で…
- 認知症の相続人がいる場合 -遺産分割の問題 認知症の相続人がいる場合遺産分割の問題 相続人の1人が老人性痴ほう症になっている場合も、特別な配慮が必要です。 遺産分割は共同相続人が相続した財産の権利の移転または処分を伴う法律行為であるために、有効な遺産分割を行うためには、相続人全員が有効に法律行為を行うことができる意思能力と行為能力を有していることが必要となります。ただし、老人性痴ほう症といっても、程度は様々で、老人性痴ほう症…
- 調査方法 -相続財産の確定 調査方法相続財産の確定 被相続人の財産を生前から相続人や同居者が管理していた場合には、その把握も比較的簡単にできますが、被相続人自身が1人暮らしであった場合や財産を自ら管理していた場合、同居者が協力に応じてくれない場合などは、相続財産が明確にならない場合も多々あります。そのような場合は、さまざまな資料を手掛かりに財産調査を行う必要があります。もっとも相続財産といっても、どこにあるか…
- 財産の一部が抜けたままなされた遺産分割 -遺産分割の問題 財産の一部が抜けたままなされた遺産分割遺産分割の問題 遺産分割協議成立後になって、未分割の遺産が存することが判明することがあります。この場合に遺産分割協議を無効として全遺産を再分割すべきか、新たに判明した遺産のみを分割すればよいかが問題となります。 当初の分割協議が無効となる場合 まず、遺産分割の対象から抜けていた遺産が重要で、当事者がその遺産のある…
- 遺産の管理 遺産の管理遺産の管理 相続が開始すると、遺産分割により具体的な遺産の所有者が決まるまでの間、共同相続人はその相続分に応じて遺産を共有することになります。各共有者はその持分に応じて相続財産を使用することができ、その間遺産の管理を行うことになります。遺産の管理としては、下記のような保存行為、管理行為、処分行為があげられます。遺産の保存行為は各人が単独で行うことができる行為であり、管理行…
- 遺産の管理に関するトラブル -遺産の管理 遺産の管理に関するトラブル遺産の管理 相続人の1人が遺産の不動産を占有している場合 相続財産に不動産が含まれる場合、原則として相続開始により当該不動産は共同相続人の共有となり、その持分に応じて相続財産の使用・収益をうける権利が発生します。相続財産に不動産が含まれる場合で、例えば当該不動産が家屋で、その家屋に1人の相続人が被相続人と同居していたというケースはでは注意する点があ…
- 遺産の管理費用 -遺産の管理 遺産の管理費用遺産の管理 共同相続人が全員で遺産管理を行う場合、遺産分割協議や調停・審判の終了までの間、遺産の管理にかかった費用は、相続財産から出します。ただし、相続人の過失によって発生した費用は、この限りではありません。管理費用として認められるのは、相続財産に係る固定資産税や地代、賃料、上下水道料金、電気料金、火災保険料などです。土地改良費や増資払込金等株式取得費用、相続…
- 遺産分割について -よくある質問 遺産分割Q&A 遺産分割についてよくある質問 遺言Q&A 遺産分割とは何ですか? 遺産の分割とは、相続開始後に共同相続人の共有または合有となっている相続財産について、誰が何を相続により取得するかを決定して、各共同相続人の単独所有または真の意味での共有とすることをいいます。遺産分割協議が各相続人の自由意思に基づく合意による限り、法定相続分を超える分割もすることができます。 遺産分割が…
- 遺産分割の対象にならない財産 -相続財産の確定 遺産分割の対象にならない財産相続財産の確定 年金受給権 公営住宅の使用権 墓地などの祭祀承継 年金受給権 年金受給権は遺産分割の対象となりません。 被相続人が掛け金または保険料を負担した後に被相続人が死亡し、相続後にその遺族が年金の支払いを受けることがありますが、それが公的…
- 遺産分割の対象になる財産 -相続財産の確定遺産分割の対象になる財産相続財産の確定 不動産 金銭債権(預貯金等) 借地権・借家権 損害賠償請求権 動産 金銭債務(借金) 不動産 不動産(土地と建物)は当然に遺産分割の対象となります。 相続が開始すると相続財産はいったん相続人全員の共…
- 遺産分割の際に意思表示に瑕疵があった場合 -遺産分割の問題 遺産分割の際に意思表示に瑕疵があった場合遺産分割の問題 遺産分割協議は、共同相続人全員の意思の合致により成立しますが、意思表示が詐欺・脅迫による場合や錯誤による場合には、無効・取消しの主張ができます。 この場合、瑕疵(詐欺や強迫、錯誤など)について相続人間で争いがなければ分割協議のやり直しということになりますが、この点について争いがあれば家事審判または民事訴訟で争うことになります。…
- 遺産分割協議中に遺産の価格が変動してしまった場合 -遺産分割の問題 遺産分割協議中に遺産の価格が変動してしまった場合遺産分割の問題 遺産分割の話し合いに時間がかかってしまった場合に、不動産や株券などの財産の価値が変動する場合があります。このような場合、どのように遺産の価値を評価するかが問題になります。遺産分割の際の遺産の評価方法は時価によるとされています。預金などの債権は原則として債権総額により、株式は上場されていればその取引価格により、非上場の株…
- 遺産分割協議書の文例 -遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書の文例遺産分割協議書の作成 遺産分割のケースごとに遺産分割協議書の書き方は異なります。遺産分割に強い相続弁護士・東京永田町法律事務所が監修した遺産分割協議書の文例をご参考にしてください。 ケースごと 遺産分割協議書1相続人の1人が遺産の全部を取得するケース 遺産分割協議書2相続人ごとに相続…
- 遺産分割協議通りの履行がなされない -遺産分割の問題 遺産分割協議通りの履行がなされない場合遺産分割の問題 遺産分割協議書どおりの遺産分割の実現に他の相続人の協力が必要な場合があります。例えば、代償相続によって遺産分割が成立した場合、多くの財産を相続した相続人は、他の相続人に対して、代賞金を支払う負担(債務の負担)の義務を負うのですが、債務の負担がなされない場合があります。この場合負担者が履行しないからといって、他の相続人は債務の不履…
- 遺産分割審判による分割 -遺産分割の方法 遺産分割審判による分割遺産分割の方法 遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割審判手続に移行します。審判とは、家庭裁判所の審判官が相続人の主張や遺産の内容を客観的に判断して、遺産の分割について決定を出す分割の方法です。審判分割においては、民法906条の分割基準に従って、「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮…
- 遺産分割対象にならない場合がある財産 -相続財産の確定 遺産分割対象にならない場合がある財産相続財産の確定 株式 ゴルフ会員権 生命保険死亡退職金形見分けの品 生前贈与 株式 株式は必ずしも遺産分割協議の対象にはなりません。 株式も預貯金債権と同様、相続分に応じて分割され、必ずしも遺産分割協議の対象にはなりませんが、預貯金債権と同様に一般的には遺産分割…
- 遺産分割後に遺言がみつかった場合 -遺産分割の問題 遺産分割後に遺言がみつかった場合遺産分割の問題 遺産分割協議で遺産分割をし、相続手続きを済ませた後に、被相続人の遺言が判明し、トラブルになることがあります。出てきた遺言が有効なものであれば、原則として遺言が優先しますが、遺言が無効なものであれば、そもそも問題にはなりません。 相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容を正しく理解した上で、全員の同意をもって、遺言に反する遺産分割協議を…
- 遺産分割成立まででよくあるトラブル -よくある質問 遺産分割Q&A よくあるトラブル(遺産分割成立まで)よくある質問 遺言Q&A 遺言が2つ出てきた場合はどうすればよいですか? 原則として、遺言者の死亡した時点に一番近い時期に作成された遺言が効力を持つとされ、前後2通の遺言で同じ事柄について、異なる処分をしている場合には、後の遺言で前の遺言が変更されたとみなされます。この場合抵触する部分についてのみ取消されただけで、前の遺言の全てが取消され…
- 遺産分割成立後のよくあるトラブル -よくある質問 遺産分割Q&A よくあるトラブル(遺産分割成立後)よくある質問 遺言Q&A 遺産分割後に遺言が見つかった場合どうすればよいですか? 分割協議で遺産分割をした後に遺言が出てきたときは、原則として遺言が優先します。もっとも、相続人全員の合意で遺言に反する遺産分割協議をすることができますので、すでに行った遺産分割協議を維持することも可能です。相続人のうち1人でも、見つかった遺言を理由に遺産分割協…
- 遺産分割調停、遺産分割の方法など -よくある質問 遺産分割Q&A 遺産分割の方法よくある質問 遺言Q&A 遺産を分けるにはどのような方法がありますか? 遺産分割の方法として、遺言、協議、調停、審判による方法があります。まず、遺言があれば、遺言が一番に優先されます。遺言がない場合は、相続人全員での協議で決定されます。協議が調わないときや協議ができないときは、家庭裁判所における調停もしくは審判で定めることになります。 相続人が全員揃わ…
- 遺産分割調停による分割 -遺産分割の方法 遺産分割調停による分割遺産分割の方法 遺産分割協議がまとまらない場合は、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。相続人の1人、もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てます。遺産分割調停では、調停委員(裁判官1人と調停委員2人)が間に入り、各相続人の言い分を聞いた上で、客観的に妥当な方向性や相続分を示し、共同相続人間の話し合いが円滑に行える…
- 遺産確認での遺産分割の対象財産・非対象財産 -相続財産の確定 遺産分割の対象となる財産とならない財産相続財産の確定 遺産分割の対象になる財産 不動産 金銭債権(預貯金等) 借地権・借家権 損害賠償請求権 動産 金銭債務(借金) …
- 遺留分について -よくある質問 遺産分割Q&A 遺留分についてよくある質問 遺言Q&A 遺留分とは何ですか? 遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定割合をいいます。遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合には相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1となっています。 遺留分を無視した遺言は無効で…
- 遺留分の放棄 -遺留分 遺留分の放棄遺留分 遺留分は相続放棄とは違って、相続開始前に遺留分放棄することができます。ただし、遺留分を放棄するためには、遺留分権利者が家庭裁判所に申立てをすることが必要で、かつ家庭裁判所の許可を受けたときに限り、放棄の効力が生じます。わざわざ家庭裁判所の許可を要するのは、被相続人や他の相続人の強制など、本人の意思に反する放棄を防止するためです。 遺留分放…
- 遺留分の算定方法 -遺留分 遺留分の算定方法遺留分 遺留分算定の基礎となる財産の額に、遺留分の割合をかけた額が遺留分です。基礎となる財産の価格は、原則として相続開始時に存在する財産に、被相続人が相続開始前1年以内に贈与した財産等を加え、これらから相続債務を引いたものです。寄与分が考慮されないこと、相続債務が控除されること等の点で「みなし相続財産」や「具体的相続分」の算定とは異なりますので注意しましょう…
- 遺留分権利者と遺留分 -遺留分 遺留分権利者と遺留分遺留分 遺留分があるのは、推定相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)であり、兄弟姉妹以外の相続人です。相続欠格者、廃除された者、相続放棄をした者は、相続権を失ったことで遺留分もなくなります。ただし、相続欠格、廃除の場合は代襲相続人が遺留分権利者となります。遺留分の割合は、父母(直系尊属)のみが相続人であるときは3分の1、その他は2分の1となります。こ…
- 遺留分減殺請求の対象・範囲・効果 -遺留分 遺留分減殺請求の対象と範囲と効果遺留分 遺留分減殺請求の対象となる処分行為は遺贈と贈与です。減殺を行う場合は、必ず第1に遺贈、第2に贈与の順で減殺しなくてはいけません。またその他に遺言による相続分の指定、遺産分割方法の指定も減殺の対象になります。 遺 贈 遺贈には包括遺贈と特定遺贈とがありますが、いずれも遺留分減殺請求の対象になります。減殺すべき遺贈が複数ある場合に…
- 遺留分減殺請求の方法 -遺留分 遺留分減殺請求の方法遺留分 遺留分を侵害する遺言や贈与は当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が相手方に対し遺留分減殺請求をして初めて遺留分を取り戻すことができます。つまり、遺留分を侵害された相続人は、ただ放っておくだけでは侵害された遺留分を取り戻せません。遺留分減殺請求を行うことができるのは、遺留分権利者とその承継人です。その相手方は、遺留分を侵害している受遺者、受贈…
- 遺言と遺産分割の関係 -よくある質問 遺産分割Q&A 遺言と遺産分割の関係よくある質問 遺言Q&A 遺産分割にあたって、まず何から行えばよいですか? まず、遺言があるかどうかを確認します。遺言の有無やその内容によって遺産分割の内容が全く違ってきますので、必ず初めに遺言の有無を確認しましょう。 紛失した遺言を捜し出すことはできますか? 遺言者が公正証書で遺言を作成していた場合は公証役場の検索システムで捜すことがで…
- 遺言による遺産分割 -遺産分割の方法 遺言による遺産分割遺産分割の方法 1 遺言は遺産分割に優先 2 遺言の種類と調査方法 3 遺言の検認手続 4 遺言の有効性を争う場合 5 遺言による遺産分割についての問題 …
- 遺言による遺産分割 遺言による遺産分割遺産分割の方法 1 遺言は遺産分割に優先 2 遺言の種類と調査方法 3 遺言の検認手続 4 遺言の有効性を争う場合 5 遺言による遺産分割についての問題 遺言は遺産分割に優先 被相続人の遺言が見つかった場合は、遺…
- 遺言を無視した遺産分割をしたい場合 -遺産分割の問題 遺言を無視した遺産分割をしたい場合遺産分割の問題 遺言がある場合は、遺言が遺産分割に優先します。しかし遺言の内容が全相続人の意向とは全く違っている場合もありますので、遺言を無視して、相続人全員で遺産分割を行いたいと考える場合も考えられます。 相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容を正しく理解した上で、全員の同意をもって、遺言の内容と異なる協議を行えば、遺産分割を遺言に優先させるこ…
- 限定承認 -相続の放棄と承認 限定承認相続の放棄と承認 相続の限定承認とは、相続財産の範囲内のみで債務の承継をするという条件付相続をいいます。被相続人に積極財産もあるが、消極財産(借金など)もあり、全体でプラスになるのかマイナスになるのか明らかなではないときに、相続財産の範囲内のみで借金などを清算し、もし残金があれば相続するという制度です。例えば、相続財産が500万円で、相続債務が800万円の場合、限定…
- 限定承認、相続放棄について -よくある質問 遺産分割Q&A 相続するかどうか(単純承認・相続放棄・限定承認)よくある質問 遺言Q&A 相続する場合はどのような手続が必要ですか? 限定承認や相続放棄をしないで、相続人が被相続人の財産を無条件で相続することを「単純承認」といいます。単純承認には限定承認や相続放棄のような特別の法的手続きは必要ありません。相続開始から3か月が経過することで当然に相続を承認したことになります。 相続し…
- 預貯金等の相続 -遺産分割後の手続き 預貯金等の相続遺産分割後の手続き 相続の開始を金融機関が知ると、被相続人名義の預貯金はいったん凍結されますので、その引出しを行う場合は、払戻しまたは名義変更の手続きが必要となります。被相続人の預貯金債権は、相続の開始と同時に法定相続分に応じて分割され各相続人に移転し、遺産分割後は遺産分割の内容に従って各相続人に相続開始にさかのぼって移転するとされています。つまり相続人は金融機関に…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
| 内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) | ||
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。