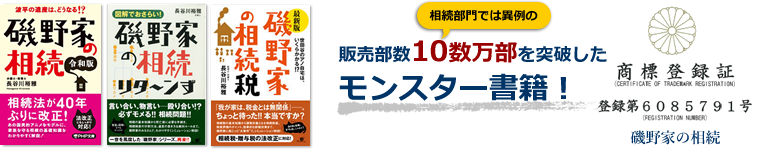カテゴリー:『 知識の解説 』の記事一覧
- 知識の解説 不動産相続トラブルのポイントや不動産相続に関する法律用語の解説を紹介しています。 相続における不動産の重要性 弁護士が扱う相続トラブルは、ほぼ100%不動産が関係しています。資産構成や評価の複雑さ、思い入れや賃貸借権、換金性など、相続における不動産特有の問題点について解説します。 1.なぜ相続で不動産が…
- 1.なぜ相続で不動産が重要なのか 1.なぜ相続で不動産が重要なのか相続における不動産の重要性 大部分が不動産 夢のマイホーム。人生で一番高い買い物と言われる不動産。何千万円もする買い物ですし、一生のうちで何回も不動産を購入する機会に恵まれる方は多くはないでしょう。住宅ローンを何十年もかけて支払い続ける。定年間近にやっと支払いが終わる。あるいは定年を越えても支払いが続く。給料の大部分が住宅ローンに消えて…
- 1.不動産と現金の価格は同じか 1.不動産と現金の価格は同じか不動産を利用した節税対策 同じ「1億円」ではない 1億円の現金と1億円の不動産、あなたなら相続財産としてどちらを残しますか。現金のメリットは、何と言っても流動性に富んでいることです。たとえば、交通事故に遭い、手術費として急に現金が必要になった場合に1億円の現金を相続していれば、銀行から引き出してすぐにそれを手術費に充てることができます。一…
- 1.改正により納税者は増える 1.改正により納税者は増える不動産にかかる相続税 「現下の経済情勢等を踏まえ、『成長と富の創出の好循環』の実現、社会保障・税一体改革の着実な実施、震災からの復興の支援等のため」(財務省HPより)に税制が改正されました。この平成25年度改正によって、相続税の対象となる相続件数は4%程度ですが、「基礎控除額」の引き下げによりその割合が6%程度にまで引き上げられるといわれています。基…
- 1.相続登記 1.相続登記不動産を相続した時の各種手続 相続が発生すると、被相続人の不動産は相続人の共有状態になり、遺産分割を経て、不動産は取得する相続人のものになります。所有者が被相続人のままになった不動産登記は名義変更の手続きが必要になります。被相続人名義の不動産を取得した相続人に変更する手続のことを相続登記といいます。相続登記は法律上、いつまでにやらなければいけないという期限が決めら…
- 2.土地の権利証 2.土地の権利証不動産を相続した時の各種手続 土地の権利証とは、不動産について登記が完了したことを証する登記済証、法務局の印鑑を押した書類をいいます。権利証自体は、登記手続きが終わったことを証するものであり、本来は不動産の所有者が誰かということの証明書ではありません。登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための確認手段の1つにすぎません。ただし、権利証を持っているこ…
- 2.必ず活用すべき「小規模宅地等の特例」 2.必ず活用すべき「小規模宅地等の特例」不動産を利用した節税対策 小規模宅地等の特例を利用できる場合 不動産は相続財産のうち大部分を占めますので、それなりの金額の相続税がかかります。せっかく不動産を相続しても相続税の支払いのためにその不動産を手放さなければならない、ということにならないように、一定の条件を満たす場合には不動産の評価額を80%減額とする特例があります。こ…
- 2.相続税の計算のしくみを知る 2.相続税の計算のしくみを知る不動産にかかる相続税 相続税の計算は次のような流れで計算されます。おおまかな流れを知っておくと、相続税対策に役立ちます。 相続税の計算の流れ 【ステップ1】相続税が発生するかどうか不動産にかかる相続税 正味の遺産額(課税価格)から基礎控除額を差し引いて、相続税の課税対象となる財産である課税遺産総額を計算して…
- 2.相続財産のほとんどが不動産の理由 2.相続財産のほとんどが不動産の理由相続における不動産の重要性 人生で一番高い買い物 多くの人にとって不動産が一生で一番高い買い物であるのは間違いありません。地域や広さによって価格が大きく変化するため一概には言えませんが、住宅金融支援機構が実施している「フラット35利用者調査(平成24年度)」の統計によると、土地付注文住宅の全国平均価格は約3562万円で、最高は東京…
- 3.不動産の評価が複雑な理由 3.不動産の評価が複雑な理由相続における不動産の重要性 不動産の評価に絶対はない 「指値」という言葉がありますが、賃貸でも売買でも値切り交渉が前提になっています。日本のような先進国において、値切り交渉が可能な商品は不動産以外にはなかなか思いつきません。このため、ある不動産がいくらなのかを正確に算出することは不可能です。同じ不動産であっても売り急いでいる売主であれば安く…
- 3.不動産業者との媒介契約 3.不動産業者との媒介契約不動産を相続した時の各種手続 遺産分割協議で取得した不動産を売却する、あるいは換価分割で不動産を売却する場合には、不動産業者との媒介契約を締結することになります。媒介契約とは、宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の仲介の依頼を受ける際、依頼者との間で締結する契約をいいます。この媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり…
- 3.人に貸しているだけで評価減 3.人に貸しているだけで評価減不動産を利用した節税対策 人に土地を貸している場合 小規模宅地等の特例を利用できない土地であっても、相続税評価額を低くなる場合があります。人に土地を貸している場合、いくらその土地が自分名義の土地であっても、「すぐに建物を壊して更地に戻して出て行ってくれ」ということはできません。所有権があっても利用に強い制限がかかります。このような土地を貸…
- 3.相続財産を評価しなければ始まらない 3.相続財産を評価しなければ始まらない不動産にかかる相続税 相続財産の評価の仕方にはルールがあります。特に節税効果が高い不動産についての評価の方法を知ると知らないとでは相続税対策に違いが出てきます。 土地の評価 土地を評価するために路線価を用います。路線価とは、その道路に接する標準的な宅地の評価額の基準になるものです。道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価…
- 4.一戸建てとマンションではどちらが得か 4.一戸建てとマンションではどちらが得か不動産を利用した節税対策 一戸建てを売りに出していた外国人が、自分の家と同じくらいの広さのマンションを引合いに出し、どうして日本ではマンションの方が一戸建てに比べて高めに評価されているのかと不満を漏らしていました。持っている一戸建てがなかなか売れない。近所のマンションは自分の一戸建て以上の値段がついているにもかかわらず、どんどん売れてい…
- 4.不動産売買の仲介手数料 4.不動産売買の仲介手数料不動産を相続した時の各種手続 仲介手数料とは、不動産業者を通して不動産を売買あるいは賃借する場合に、不動産業者に報酬として支払うお金をいいます。媒介手数料もしくは媒介報酬ともいいます。仲介手数料は、売買もしくは賃貸借の成約時に成功報酬として支払うもので、依頼や申込み段階では発生しませんし、契約が無効・取消しとなったときも、不動産業者は請求することはで…
- 4.土地の状態によって相続税の評価額が左右 4.土地の状態によって相続税の評価額が左右不動産にかかる相続税 現金100万円という場合、一万円札100枚か1円玉100万枚かといった違いはあるかもしれませんが、100万円という価値に違いはありません。一方、400㎡の土地といった場合、縦20m×横20mの正方形かもしれませんし、幅5メートル奥行き80mのウナギの寝床のような長方形かもしれませんし、はたまた50×16の三角形かも…
- 4.思い入れが強い不動産がトラブルのきっかけに 4.思い入れが強い不動産がトラブルのきっかけに相続における不動産の重要性 思い入れが相続を困難に 不動産は、生活の場そのものになることから、思い入れが強くなります。生まれ育った家であれば柱の傷が幼少時の思い出を思い起こさせますし、長年手をかけリフォームを重ねた場合には、あれこれ考えて費やした時間が結実したことが費用以上の意味を持ちます。そのため、愛着のある家を手放す…
- 5.タワーマンション1階と最上階ではどちらが得か 5.タワーマンション1階と最上階ではどちらが得か不動産を利用した節税対策 タワーマンションの販売が活況のようです。注目の新築物件として紹介されているのが都心のタワーマンションです。ショールームでは外国製の家具が配置されていて、水栓金具ひとつとっても輸入ものを使用して高級感を演出しているようです。マンションが一般的ではなかったころの高層マンションの第1号は、容積率や日照権などの問…
- 5.不動産は所有権だけではない 5.不動産は所有権だけではない相続における不動産の重要性 借地権も相続財産に 土地の「所有権」とは、その文字のとおり、土地を所有する権利のことです。通常、売買代金を支払えば、土地の購入者が所有権を有します。所有権によって、土地を売却したり贈与したり自由に処分することができます。土地を所有すると、地代などの賃料はかかりませんが、固定資産税と都市計画税を支払う義務が生じま…
- 5.海外の不動産 5.海外の不動産不動産にかかる相続税 仕事を辞めてリタイア後に海外で暮らす日本人が増えているといいます。また投資として海外不動産への関心も高くなっています。被相続人が海外に住んでいた場合、相続人が海外に住んでいる場合、相続財産に海外の預金や不動産などが含まれていた場合は、どのような配慮が必要なのでしょうか。 法の適用に関する通則法では、相続は被相続人の本国法によるとされて…
- 5.重要事項説明書の説明 5.重要事項説明書の説明不動産を相続した時の各種手続 宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を締結するまでの間に、不動産会社は購入予定者に対して物件と取引について重要事項の説明をしなければならないとされています。重要事項説明は宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証を見せ、内容を記載した書面を交付した上で、口頭で説明を行います。重要事項説明書の最後には、購入予定者が署名・押…
- 6.不動産の流動性 6.不動産の流動性相続における不動産の重要性 流動性の高い資産 相続において流動性の高い資産を持つことは重要なポイントです。流動性が高い資産とは、つまりは現金にしやすい財産。相続財産のほとんどが不動産や中小企業の株式など流動性の低い財産の場合には、いざ現金が必要になった場合に困ります。まず直面するのは相続税の申告納付のときです。現金が用意できないために想定外の売却や不…
- 6.時価とのねじれ現象を利用 6.時価とのねじれ現象を利用不動産を利用した節税対策 相続税の節税を考えるときに、時価と相続税評価額とのギャップを利用することは重要です。たとえば、ポルシェなどの高級車。購入するときは1000万円を超える高級車ですが、すぐに値落ちしてしまいます。中古車の査定はレッドブックという本で確認ができますが、耐用年数に応じてすぐに値段が下がってきます。相続の時には値段がついていない場合…
- 7.海外の不動産と日本の不動産はどちらが得か 7.海外の不動産と日本の不動産はどちらが得か不動産を利用した節税対策 日本にある土地は、路線価方式や倍率方式によって評価されます。路線価は公示価格の約80%で計算されますので、通常は時価よりも低く設定されています。また、小規模宅地等の特例を適用することができれば、一気に評価額を下げることができます。さらに、広大地や崖地、不整形地など、使いにくい土地については評価が下がります。…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
| 内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) | ||
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。