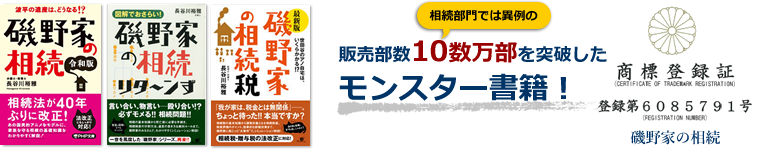相続税の計算方法相続税の税理士
- [CATEGORY]:
- 知識の解説 相続税の計算について
- [TAG]:相続税
大きく分けて3つのステップで計算
日本の相続税の計算は、相続や遺贈、死因贈与によって財産をもらったそれぞれが、もらった財産に対して税率をかけて計算するような単純な方式でありません。
日本の課税方式である「法定相続分課税方式」は少し複雑な計算方法です。この課税の考え方は、①被相続人の相続財産全体を課税対象とする考え方をしており、どのような分配の仕方を行っても、相続財産の全部が相続税の対象となること【課税の公平】、②各相続人が受け取った財産の割合に応じて平等に相続税が発生する【各相続人の公平】ように、複雑な仕組みになっています。
大きく見ると次の3つのステップで計算されます。
ステップ1 相続税が発生するかどうか
正味の遺産額(課税価格)から基礎控除額を差し引いて、相続税の課税対象となる財産である「課税遺産総額」を計算します。ここで、この相続について「相続税が発生するかどうか」を判断します。
ステップ2 相続税がどれだけ発生するか
ステップ1で計算した課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人の法定相続分で分けた場合の仮の相続税額を出した上で、「相続税の総額」を計算します。
ステップ3 各相続人等がどれだけ相続税を支払うか
ステップ2で計算した、相続税の総額を実際に行われた遺産分割の割合で按分し、各相続人に適用される「控除」を差し引くなどし、「各相続人等が納付する相続税額」を計算します。
【ステップ1】 相続税が発生するかどうか
正味の遺産額(課税価格)から基礎控除額を差し引いて、相続税の課税対象となる財産である課税遺産総額を計算して、この相続について「相続税が発生するかどうか」を判断します。
正味の遺産額(課税価格)
まず、正味の遺産額(課税価格)とは、被相続人の「(本来の)相続財産」に「みなし相続財産」と言われる財産の額、「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」、「相続開始前3年以内に受けた贈与財産」を加算し、「非課税財産」や「相続債務」等を控除した金額を言います。
| 正味の 遺産額 (課税価格) | = | 相続 財産 | + | みなし 財産 | + | 相続時精算課税 の適用を受ける 贈与財産 | + | 相続開始前 3年以内に 受けた贈与財産 | - | 非課税財産 相続債務 葬式費用 |
基礎控除額
相続や遺贈などによって財産を相続したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。
目安としては、「正味の遺産額(課税価格)」と「基礎控除額」と言われる金額を比べた場合に、基礎控除額の方が多い場合は、相続税がかからないことになります。相続税がかからないということは、相続税を支払う必要はありませんので、相続税の申告をする必要もなくなります。
一方、正味の遺産額の方が多い場合は、相続税がかかります。正味の遺産額(課税価格)から基礎控除額を差し引いて残る額を「課税遺産総額」といい、この金額に対して相続税が課税されます。
【基礎控除額】 3000万円+(600万円×法定相続人の数)
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3600万円 |
| 2人 | 4200万円 |
| 3人 | 4800万円 |
| 4人 | 5400万円 |
| 5人 | 6000万円 |
| 6人 | 6600万円 |
相続放棄をした法定相続人がいる場合の「法定相続人の数」
基礎控除額は、「法定相続人の数」によって金額が違います。 では、相続人の1人が相続放棄をしている場合はどうなるのでしょうか。法定相続人が相続放棄をした場合、民法上は、初めから相続人ではなかったということになります。
例えば、被相続人Xに、妻A、子B、子Cがいる場合は、法定相続人は3人です。ところが何らかの理由で、子Cが相続放棄をしたとします。相続放棄した子Cは、相続開始時に遡って相続人ではなくなりますので、法定相続人の数は、妻Aと子Bの2人となります。実際に相続財産を受け取る人数は2人ですが、基礎控除額計算の「法定相続人の数」は3人のままです。
基礎控除額を計算する場合の「法定相続人の数」は、相続放棄をした人がいたとしても、相続開始時の法定相続人の数にて計算します。
法定相続人に養子がいる場合の「法定相続人の数」
相続人に養子が含まれる場合は注意が必要です。
例えば、妻A、実子B、実子Cがいる被相続人Xが、さらに養子D、養子Eと養子縁組をしていたとします。民法上は、養子も法定相続人にあたりますので、実子と同様の相続分を相続することが出来ます。つまり、この場合、妻A、実子B、実子C、養子D、養子E、計5人が法定相続人になります。
ただし、この場合、この5人という数が「法定相続人の数」としてカウントされるわけではありません。法定相続人に養子がいる場合は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人を限度としてカウントすることができます。つまり、養子のうち1人しか「法定相続人の数」にカウントされませんので、基礎控除額は、3000万円+600万円×4人で、5400万円となります。
「法定相続人の数」に制限をかけている理由は、不当に養子縁組を行って基礎控除額を高くしようすることを阻止するためです。もちろん被相続人にその意思がなくとも、実子がいる場合は、カウントできる養子の数は1人となります。
なお、この場合の「養子」は普通養子であり、特別養子は含みません。
【ステップ2】相続税がどれだけ発生するか
正味の遺産額(課税価格)から基礎控除額を差し引き、残額(課税遺産総額)がある場合、つまり、正味の遺産額(課税価格)が基礎控除額より多い場合は、相続税を支払う必要があります。
相続税が発生することが分かったら、次に、この相続に係る「相続税の総額」を計算します。
まず、「課税遺産総額」を、各法定相続人の「法定相続分」に従って分配した額を計算します。
次に、各法定相続人の法定相続分に従った分配財産の額に該当する「税率」をかけて、各法定相続人の仮の相続税額を計算します。
そして、各法定相続人の相続税額を合算し、「相続税の総額」を計算します。
法定相続分に従って相続したと仮定して計算
「相続税の総額」の計算においては、仮に法定相続分に従って相続した場合、で考えます。
つまり、実際に法定相続分と違う内容で遺産分割を行った場合でも、遺言で法定相続分と違う相続分の指定があった場合でも、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合でも・・・、その割合は関係ありません。とにかく、相続が開始した時点での法定相続人の「法定相続分」で計算すればよいのです。
法定相続人と法定相続分
| 法定相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 配偶者と子がいる | 配偶者 | 2分の1 |
| 子 | 2分の1(複数いる場合は均等分割) | |
| 子がいない場合で 配偶者と父母がいる | 配偶者 | 3分の2 |
| 父母 | 3分の1(複数いる場合は均等分割) | |
| 子も父母もいない場合で 配偶者と兄弟姉妹がいる | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1(複数いる場合は均等分割) | |
各相続人の仮の相続税額を計算
各法定相続人の「法定相続分に従った分配財産」(仮の相続分)を算出したら、仮の相続分に該当する法律で決まった相続税の税率を掛け、控除額を差し引いて各法定相続人の「仮の相続税額」を計算します。
相続税の税率
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税 率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の総額計算
各法定相続人の仮の相続税額を足して、「相続税の総額」を計算します。
例えば、被相続人Xの課税遺産総額が1億2000万円で、相続人が妻Aと子B、子Cの場合。
妻Aの法定相続分は2分の1、子の法定相続分はそれぞれ4分の1(例えば、子Cが相続放棄しても、この相続分に影響はありません。)となり、法定相続分通り計算しますと、各相続人が「仮に相続する財産」は、妻Aは6000万円、子B、Cはそれぞれ3000万円となります。
妻Aの相続分は6000万円なので税率は30%、控除額は700万円、子B、Cらの相続分は各3000万円なので税率は15%、控除額は50万円となります。法定相続分に従った妻Aの相続税額は1100万円、子B、Cそれぞれは400万円ということになります。
- 妻A 1億2000万円×1/2×30%-700万円=1100万円
- 子B 1億2000万円×1/4×15%- 50万円= 400万円
- 子C 1億2000万円×1/4×15%- 50万円= 400万円
相続税の総額 1100万円+400万円+400万円=1900万円
この相続において発生する「相続税の総額」は、1900万円になります。
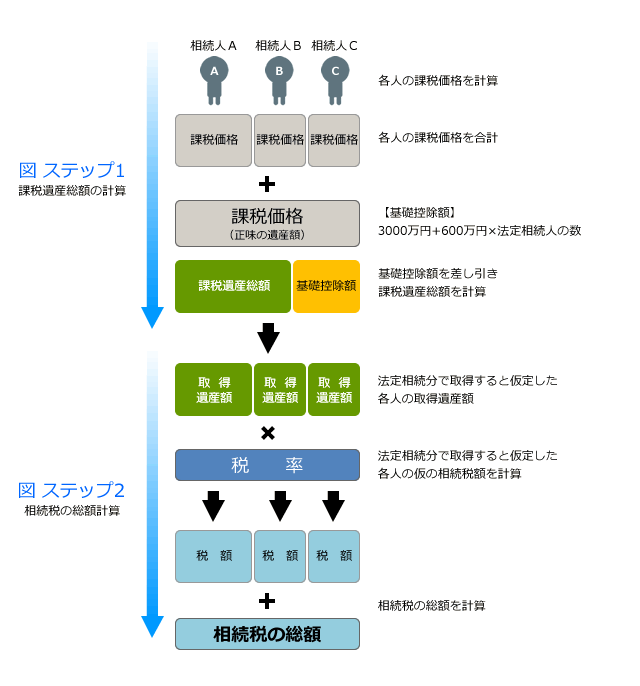 PAGE TOP
PAGE TOP
【ステップ3】各相続人等がどれだけ相続税を支払うか
「相続税の総額」が分かったら、実際に誰がどれだけ支払うかを決定します。
「相続税の総額」は、仮に相続人が法定相続分どおりに従って財産を受け継いだとしたらと、あくまでも仮定の計算として行いました。遺産分割や遺言の相続指定で実際に受取る割合が決定したら、「相続税の総額」をその割合で分配して割り出し、各法定相続人らが支払う税額を計算します。
| 【各相続人等が支払う納税】 | = | 相続税の総額 | × | 各相続人の課税価格 課税価格の合計額 |
例えば、被相続人Xの課税遺産総額が1億2000万円で、相続人が妻Aと子B、子Cの場合。
遺産分割の結果、妻Aが9600万円、子B、子Cが各1200万円を相続したとしますと、相続税の総額は、ステップ2で計算したとおり1900万円ですので、各人が支払う相続税は、妻Aは1520万円、子B、Cはそれぞれ190万円となります。
- 妻A 1900万円×9600万円/1億2000万円=1520万円
- 子B 1900万円×1200万円/1億2000万円= 190万円
- 子C 1900万円×1200万円/1億2000万円= 190万円
税額控除とは
実は、【ステップ1】から【ステップ3】までの計算で、相続額が決定という訳ではありません。
ステップ3で計算された各相続人等の相続税額から、さらに差し引くことができる控除がある場合がります。それを、「税額控除」といいます。
税額控除は、各相続人等の立場を考慮した控除であり、主なものとして、配偶者の税額の軽減(配偶者控除)、未成年者控除、贈与税額控除、障害者控除などがあります。
この税額控除によっては、「被相続人の単位で相続税が発生」となっても、「相続人の単位で相続税が発生しない」ということがあり得ます。つまり、税額控除次第で、結果として相続税を支払わなくてもよい相続人が発生することになります。
1 配偶者の税額の軽減(配偶者控除)
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した財産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が被相続人の財産を法定相続分どおり相続すると、相続税がかからないことになります。もし、その金額を超えて相続財産をもらったとしても、1億6000万円以下であれば相続税は発生しません。いずれかの金額を超える場合は、その超えた金額について相続税は支払わなくてはいけません。
配偶者の税額の軽減とは、配偶者の財産形成への貢献、配偶者の生活保障を考慮して設けられた特例です。この税額控除には婚姻期間による制限はありません。極端なことをいうと婚姻期間が1日でもこの特例を受けることが出来ます。
配偶者の税額軽減を受けるためには納税申告の際に、別途手続をしなければいけません。
この配偶者の税額軽減は、遺産分割などで実際に取得した正味の遺産額(課税価格)を基に計算されることになっていますので、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。その場合は分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求の手続を行う必要があります。
2 未成年者の税額控除(未成年者控除)
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。これを未成年者控除といいます。働いていない未成年にとっては、亡くなった人から相続した財産は、今後の生活を左右する大事な財産となりますので、その点を考慮した税額控除です。
次のすべての条件に当てはまる場合は未成年者控除を受けることが出来ます。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である法定相続人
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人、または、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人(未成年者が日本国籍を有している/未成年者または被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有した場合)
控除できる額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。1年未満の期間については、切り上げて1年として計算します。
例えば、未成年相続人が12歳5か月だとすると、成人20歳になるまで7年と7か月の期間がありますが、7か月を1年に切り上げますので、期間は8年になりますので、未成年控除額は10万円×8年で80万円となります。
なお、未成年者控除額が当該未成年者の相続税額より大きい場合は、その残りの控除額については、未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。ただし、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
3 障害者の税額控除(障害者控除)
相続や遺贈によって財産をもらった相続人が85歳未満で、かつ障害者である場合には、一定の金額の控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
次のすべての条件に当てはまる場合は障害者控除を受けることが出来ます。
- 相続や遺贈で財産を取得した人が相続時に障害者である法定相続人
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
控除できる額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者については1年につき20万円)で計算します。年数の計算は未成年控除と同様に、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きい場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
4 (暦年課税分)贈与税額控除
相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与時の価額を、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加えて計算することになっています。そうなると同じ財産について生前に支払った贈与税と相続の際の相続税が、二重に課せられることになります。この不都合を回避するために、生前に支払った贈与税は、相続税から控除して調整をおこないます。これを(暦年課税分)贈与税額控除といいます。
加算される贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に受けた贈与財産。
3年以内であれば贈与の金額に関係なく加算するため、基礎控除額の110万円以下の贈与財産についても加算されます。贈与税の配偶者控除を受けている財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はありません。
控除する贈与税額
相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額。
加算税や延滞税の額は含まれません。
5 相次相続控除
父が亡くなった直後に、母が追うように亡くなってしまう。短い間に、相続が2回以上続くことは決して珍しくはありません。このように相次いで財産の相続をうけることを相次相続(そうじそうぞく)といいます。
相続が短期間に重なると、前の相続で相続税がかかった財産に、またすぐ相続税がかかることになり、相続人に一度に2重の負担がかかることになります。この負担を軽くするために、相次相続控除という制度が設けられています。
1回目の相続(これを第1次相続といいます。)とその後に来る2回目の相続(これを第2次相続といいます。)の間が10年以内の場合に、第2次相続の相続人の相続税の一定の額を控除することができます。ただし、この制度の適用は法定相続人に限られています。相続を放棄した者などが、遺贈を受けたとしても、相次相続控除の規定は適用されません。
6 外国税額控除
被相続人が海外に財産を持っている場合もありえます。この場合も海外の財産については相続税がかかります。ただし、その財産がある国で日本と同様に相続税に相当する税金がかかる場合があります。そうなると同じ財産に対して、双方の国に税金を納めなくてはいけなくなりますので、外国で相続税額がかかる場合は、日本での計算の際に差し引くことが出来ます。これを外国税額控除といいます。
PAGE TOP相続税額の加算(2割加算)
相続や遺贈によって財産を取得した人が、一定の相続人等以外であるときは、その人の相続税額の2割に相当する金額を加算することになっています。これを相続税額の加算、一般的に2割加算といいます。
例えば、子供を飛び越して孫が遺贈を受けたり、被相続人の養子になった孫、兄弟姉妹などが相続したりした場合には、税額が2割多く加算されます。これは、孫が財産を取得すると相続税を1回分免れることや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされています。
- 加算される額 各相続人の相続税額×20%
2割加算の対象者
2割加算の対象となるのは、相続または遺贈に係る被相続人の配偶者と一親等の血族(代襲して相続人となった被相続人の直系卑属を含む)以外の者です。
一親等の血族とは被相続人の父母や子どもをいいます。
相続の際に、法定相続人である子の1人が既に亡くなっているような場合は、その相続人に子がいる場合は、その子(被相続人の孫)代襲相続人として、被相続人の財産を自分の親に代わって相続することが出来ます。これを代襲相続といいます。
このような場合、孫が相続することになりますが2割加算は発生しません。本来、孫は被相続人の2親等にあたりますので、2割加算の対象者になりますが、「代襲人」の場合は対象外となります。
一方、被相続人が孫を養子にしていた場合、孫は「子」として一親等の関係になりますが、もともと養子縁組をする前は被相続人の直系卑属である場合は、2割加算の対象となります。
「孫」が財産を受ける場合で、2割加算が発生する場合としない場合があることに注意しましょう。
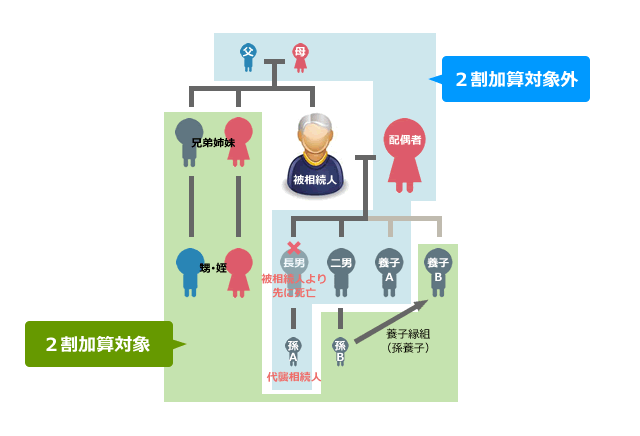
この記事と
関連性の高いページはこちら
- 2019-08-19
- [CATEGORY]: 知識の解説,相続税の計算について
- [TAG]:相続税
『 相続税の税理士 』のその他の記事
- 相続税知識の解説
- 相続税トラブルのポイントや相続税に関する法律用語の解説を紹介しています。 相続税について 相続税についての一般的な説明です。相続税の申告と納税方法について説明しています。 相続税とは相続税の申告と納税延納と物納申告・納税をしなかった場合のペナルティ 相続税の計算について 相続税がいくらになるのかを計算する方法について説明しています。一般的な計算方法のほかに、相…
- よくある質問 相続税Q&A
- 相続税の還付について 相続税の還付の手続きは面倒ですか? 実際の手続きや、税務署からの問い合わせに対する対応は当事務所で行いますので、ご依頼者様に手続きの負担を強いることはほとんどありません。相続税の還付請求の主な目的が土地評価の減額という場合、遺産分割協議書の作成や、預金や不動産の名義書き換えなどをお願いすることもありません。 最初の税理士を疑っているようで悪い気がするので、最初に相続税申告をお願いした税理士に還付請求を行ったことを知られたくありません…
- その他
- 1 養子縁組の利用 養子縁組は節税対策として利用されることがあります。養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるため基礎控除額が大きくなるためです。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますので、控除額は法定相続人の人数によって左右されます。 養子は実子と同じく「子」として相続権が発生し、法定相続人となりますので、養子縁組によって法定相続人が増え、1人につき基礎控除額が600万円増えることになります。ただし、養子の数には制限があります。 被相続人に実子…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
| 内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) | ||
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。