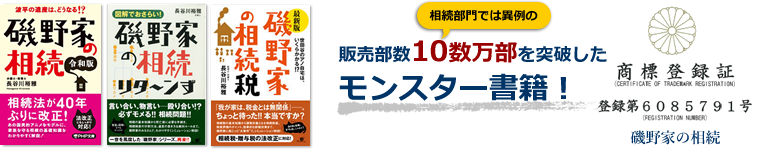カテゴリー:『 知識の解説 』の記事一覧
- 公正証書遺言 -よくある質問 遺言Q&A 公正証書遺言よくある質問 遺言Q&A 公正証書遺言とはなんですか? 公証役場で、公証人1人と証人2人の下に作成される遺言方式です。もっとも安心・確実な遺言方式といえます。 公正証書遺言のメリットはなんでしょうか? 公正証書遺言のメリットとして、1. 要件不備の不安がなく、確実な遺言をおこなえること、2. 第三者によって変造・偽造される可能性が低いこと、3.…
- 寄与分、特別受益など -よくある質問 遺言Q&A 寄与分、特別受益などの遺言・相続についてよくある質問 遺言Q&A 遺言とはなんですか? 遺言とは、法律で定められた事項(法定遺言事項)について、法律で定められた方式で、遺言者が単独でする一方的な意思表示です。 遺言を作成したほうがよいのでしょうか? 遺言を残すことで、遺言者の思い通りに財産を分けることができます。誰に何を相続させ…
- 知識の解説 遺言トラブルのポイントや遺言に関する法律用語の解説を紹介しています。 遺言を書く 遺言を残すべき人や遺言を書くタイミング、遺言の文例や遺言に類似した制度など、遺言作成を始めるにあたって知っておきたいポイント 1. 遺言を書きましょう2. 遺言を残すべき人3. 遺言を書くタイミング4. 遺言執行者とは5. 遺言の…
- 秘密証書遺言 -よくある質問 遺言Q&A 秘密証書遺言よくある質問 遺言Q&A 秘密証書遺言のメリットはなんですか? 秘密証書遺言は遺言の内容を知られることなく作成できることが最大の特徴です。また、代筆・ワープロによる作成も可能なため、自筆証書遺言より比較的簡単に作成することができます。 秘密証書遺言のデメリットはなんですか? 自筆証書遺言と同様、遺言の要件を満たしていない場合、遺言が無効となる場…
- 自筆証書遺言 -よくある質問 遺言Q&A 自筆証書遺言よくある質問 遺言Q&A 自筆証書遺言を作成する際の注意点はなんですか? 自筆証書遺言は、いつでもどこでも簡単に作成することができます。費用をかけずに自分だけで作成したい人に向いている方式です。一方デメリットが多いことも特徴です。具体的には、ワープロ等での作成ができないこと、要件を満たさない遺言は無効になる危険性があること、第三者によって変造・偽造される可能性…
- 遺言がみつかったら(検認手続など) -よくある質問 遺言Q&A 遺言がみつかったら(検認手続など)よくある質問 遺言Q&A 検認手続は必要ですか? 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は検認手続が必要ですが、公正証書遺言の場合は不要です。検認手続とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言の内容を明確にして、遺言の偽造、変造を防ぐ手続きです。遺言の内容を実現する…
- 遺言の付言事項など -よくある質問 遺言Q&A 遺言で実現できること - 遺言の付言事項などよくある質問 遺言Q&A 遺言で生命保険の受取人を変更することはできますか? 生命保険の契約者は、遺言で、保険事故発生までの間は、いつでも保険金の受取人を指定または変更することができます。保険金の受取人を指定・変更する遺言が、遺言者の死亡によって効力を生じたときは、相続人または遺言執行者はその旨を保険会社へ通知する必要があります…
- 遺言の方式について -よくある質問 遺言Q&A 遺言の方式についてよくある質問 遺言Q&A 普通方式による遺言とはどのようなものですか? 一般的な遺言の方式(普通方式)として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。いずれも法律で定められた方式に従って作成する要式行為で、必ず一定の方式に従って作成されなければ、遺言として効力を生じません。 特別方式による遺…
- 遺言の認知など -よくある質問 遺言Q&A 遺言で実現できること - 遺言の認知などよくある質問 遺言Q&A こっそりと認知することはできますか? 遺言でも認知ができますので、生前に秘密にしておくことはできます。遺言で認知をすると、相続開始と同時に認知の効力を生じます。必ず遺言執行者が、認知に関する遺言の謄本を添付して、認知の届出をしなければいけませんので、遺言執行者の指定も合わせて行います。 まだ生まれて…
- 遺言作成にあたっての注意点 -よくある質問 遺言Q&A 遺言作成にあたっての注意点よくある質問 遺言Q&A 未成年は遺言をすることはできますか? 満15歳に達していれば遺言をすることができます。ただし、満15歳に達した人でも、意思能力のない人は遺言をすることができません。遺言能力のない人のした遺言は無効です。遺言能力とは、遺言をするのに必要な意思能力をいいます。 成年被後見人は遺言をすることができますか? 成年…
- 遺言執行者など -よくある質問 遺言Q&A 遺言で実現できること - 遺言執行者などよくある質問 遺言Q&A 遺言を作成すれば、遺産分割をする必要がないのでしょうか? 遺言がある場合でも相続分しか指定していないような場合は、相続人が具体的に遺産分割を行う必要があります。例えば、●●銀行の預貯金は長男に、●●の不動産は二男に、というような内容にしておけば、遺産分割は不要になります。合わせて遺言執行者を指定しておくと、…
- 1. 相続財産について知る -遺言作成の準備の仕方 1 自分の財産について知る遺言作成の準備の仕方 財産リストを作成する まず自分の財産について整理し、財産リストを作成しましょう。家族であってもあなたの財産について、知らないということはよくあることです。もしかするとあなた自身も把握できていない財産があるかもしれません。相続リストがないと、相続開始後に相続人が調査によって調べることになります。それでは相続人に時間も労力も費用も…
- 1. 自筆証書遺言 -3つの遺言方式 1. 自筆証書遺言3つの遺言方式 自筆証書遺言はいつでもどこでも簡単に作成できることが最大の特徴です。必要なのは紙とペンと印鑑だけです。費用をかけずに、自分だけで作成したい人向きの方式です。ただし、それに伴うデメリットが多いことも特徴です。自筆証書遺言を選ぶ人は、メリットだけでなくデメリットについてよく理解しておきましょう。 メリット3つの遺言方式 …
- 1. 遺言を書きましょう -遺言を書く 1. 遺言を書きましょう遺言を書く 遺言を残す意味・・・なぜ遺言を残すのか? 「私の死後、相続人である子どもたちが、遺産分割でもめるようなことはないと思います。ですから、遺言をわざわざ残す必要がないと考えているのですが・・・。」このようにお考えの方は多くいらっしゃるのではないのでしょうか。莫大な財産があるわけではないので争いなど生じる訳がないとか、子供たちは仲が良いのでわ…
- 1. 遺言を見つけた(検認手続きの方法) -相続人の立場から 遺言を見つけた場合 1 遺言を見つけた(検認手続きの方法)相続人の立場から 遺言を見つけた場合 遺言書を発見した相続人や遺言書を預かっている人が、遺言者が死亡したことを知ったときは、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申立てをします。検認手続は相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造…
- 10. 遺言を作成したあと -遺言作成の準備の仕方 10 遺言を作成したあと遺言作成の準備の仕方 遺言を撤回・変更したい場合 遺言作成後に気が変わったり、誤りに気がついたりし遺言自体を撤回したり、変更したくなるということはよくあることです。遺言作成後でも、遺言の撤回・変更は遺言者の自由な意思で行うことができます。遺言の撤回・変更については次の方法が認められています。 撤回・変更の方法 遺…
- 2. だれが相続人になるのか? -遺言作成の準備の仕方 2 だれが相続人になるのか?遺言作成の準備の仕方 誰があなたの相続人になるのかを知りましょう。 まず自分の家系図を作成し、相続人リストを作りましょう。家系図は自分や子などの戸籍謄本をもとに作成します。配偶者、子(代襲相続人である孫・曾孫を含む)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)が、あなたの財産を受け渡す可能性のある関係者です。そのうちで誰が相続人になるか、その相続人の中で誰…
- 2. 公正証書遺言 -3つの遺言方式 2. 公正証書遺言3つの遺言方式 確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言をお勧めします。公証人が作成しますので、自分で筆記する必要がありません。公証人が、要件をきちんと確認しつつ作成してくれますので自筆証書遺言のように不備によって無効となる危険性がありません。公正証書遺言以外では相続の開始後に遅滞なく家庭裁判所に検印を請求する必要がありますが、公正証書遺言は検認の必要がありません。…
- 2. 複数の遺言書が見つかった -相続人の立場から 遺言を見つけた場合 2 複数の遺言書がみつかった相続人の立場から 遺言を見つけた場合 原則として遺言者の死亡した時点に一番近い時期に作成された遺言が効力を持ちます。 ただし、前後2通の遺言で同じ事柄について、異なる処分をしている場合には、後の遺言で前の遺言が変更されたとみなされます。これは抵触する部分についてのみ取り消されただけで、前の遺言の全てが取り消されるわけではありません。 また前後2通の遺言…
- 2. 遺言を残すべき人 -遺言を書く 2. 遺言を残すべき人遺言を書く こんな人は遺言を残しましょう! 次のようなケースなどは相続争いになる可能性が類型的に高いといわれます。類型的に相続人間で争いになることが多いケースでは、遺言を残すべきと考えます。 兄弟姉妹の仲が悪い場合 兄弟姉妹の仲が悪い場合に相続トラブルが多く発生します。特に被相続人と一緒に暮らしていた長男(もしくはその嫁)と他の兄弟姉妹…
- 3. 他に財産を残したい人がいるか? -遺言作成の準備の仕方 3 他に財産を残したい人がいるか?遺言作成の準備の仕方 お世話になった人はいませんか 遺言によって、相続人ではない人に対しても財産を残すことができます。これを遺贈といいます。例えば、事実婚の配偶者や、介護などでお世話になっているお嫁さんなどは相続人にあたりませんので、遺言がない限りあなたの財産を当然には受け取ることができません。また可愛がっているお孫さんも代襲相続人でない限…
- 3. 秘密証書遺言 -3つの遺言方式 3. 秘密証書遺言3つの遺言方式 秘密証書遺言は遺言の内容を、遺言者以外に知られることなく作成できることが最大の特徴です。遺言の内容を秘密にする遺言の方式としては、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つがありますが、遺言の存在自体を秘密にしなくてもよいのであれば、遺言の存在を公証してもらう秘密証書遺言の作成による方が望ましいです。また、代筆・ワープロによる作成も可能なため、比較的簡単に…
- 3 遺産分割後に遺言が見つかった! -相続人の立場から 遺言を見つけた場合 3 遺産分割後に遺言が見つかった!相続人の立場から 遺言を見つけた場合 遺産分割協議で遺産分割をし、相続手続きを済ませた後に遺言が出てきたときは、原則として遺言が優先します。もっとも相続人全員の合意で遺言に反する遺産分割協議をすることで、すでにした遺産分割協議を維持することも可能です。相続人のうち1人でも遺言を理由に遺産分割協議に異議を唱えれば遺産分割のやり直しになります。遺言で…
- 3. 遺言を書くタイミング -遺言を書く 3. 遺言を書くタイミング遺言を書く 遺言を書ける人とは? 年齢が15歳以上であること 遺言は15歳以上であれば未成年であっても誰でもできます。ただし、あくまでも本人の意思が必要です。自筆証書遺言の場合は、必ず本人が自書する必要があって、未成年の親権者であっても子に代わって書くことは許されません。仮にそのような遺言が作成されたら無効となります。 遺言能力が…
- 4 この遺言は無効なのではないか? -相続人の立場から 遺言を見つけた場合 4 この遺言は無効なのではないか?相続人の立場から 遺言を見つけた場合 被相続人の死後にいきなり、ある相続人に全財産を相続させる旨の遺言が発見されたケースもあります。遺言の内容があまりにも一方的で、ある相続人にだけに有利に書かれていた場合や痴ほう症を患っていた被相続人が遺言を残していた場合、本当に本人が書いたものであるのか疑いたくもなります。 遺言の無効を主張する場合は、遺言無効…
- 4. 誰に何を残すか? -遺言作成の準備の仕方 4 誰に何を残すか?遺言作成の準備の仕方 具体的に誰に何をどれだけ残すのかを決める 遺言には、「私の全財産の3分の1を妻○○に、3分の1を長男○○に、6分の1を次男○○、6分の1を長女に相続させる。」というように相続分の指定だけを書くことも可能です。しかし相続分の指定だけだと、遺言があったとしても、個々の相続財産の具体的配分に関して相続人等の間で遺産分割協議を行う必要があ…
- 4. 遺言執行者とは -遺言を書きましょう 4. 遺言執行者遺言を書きましょう 遺言執行者とは 遺言はその内容が実現されなければ意味がありません! 遺言執行者とは遺言者の遺言どおりに、遺言を実現してくれる人です。 遺言には各相続人以外への遺贈など、財産処分に関する遺言者の意思が書かれています。指定された人たちはその意思に従うわけですが、例えば、遺言者の一方的な遺言によって財産が特定の受遺者の手に渡る遺贈の場合など、…
- 5. 遺言で実現できることを知る -遺言作成の準備の仕方 5 遺言で実現できることを知る遺言作成の準備の仕方 遺言でそのようなことが実現できるのか? 法律上有効なのは遺言事項のみ 遺言に書いたことのうち、法律上の効力を持つのは、次の遺言事項(法定遺言事項)に限られます。つまり、遺言に法定遺言事項以外の事項を書いたとしても一般には無効であり、法的効力は生じません。 法定遺言事項 遺言事項…
- 5. 遺言の文例 -遺言を書きましょう 5. 遺言の文例 総合遺言を書きましょう 総合特定の財産を「相続させる」遺言財産の全部を「相続させる」遺言持分を「相続させる」遺言 遺言でできること 文例一覧遺言を書きましょう 子の認知未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定相続人の廃除廃除の取消し相続分の指定相続分のゼロ指定相続分の指定の委託遺産分割方法の指定(1)(2)遺産分割方法の指定の委託遺産分割の禁止特…
- 5. 遺言書が見つからない -相続人の立場から 遺言を見つけた場合 5 遺言書が見つからない相続人の立場から 遺言を見つけた場合 被相続人が遺言を残しているのは確かなのですが、どこに保管しているかわからない場合があります。この遺言が自筆証書遺言の場合は、出てこない限り内容を把握することができませんが、公正証書遺言の場合は遺言書の謄本を交付してもらうことができます。 遺言者の生存中は、公証人の守秘義務との関係で、推定相続人は公正証書遺言の原本の閲覧…
- 6. 死因贈与契約 -遺言を書きましょう 6. 死因贈与契約遺言を書きましょう そもそも死因贈与契約とは? 贈与とは、当事者の一方(贈与者)が、自分の財産を無償で受贈者に与える意思を表示し、相手方がその意思を受ける(受諾)ことによって生ずる契約をいいます。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます。つまり、「私が死んだら、これをあげます」というのが死因贈与契約です。贈与者の死亡によって効力が発生す…
- 6. 相続の手続きが複雑 -相続人の立場から 遺言を見つけた場合 6. 相続の手続きが複雑相続人の立場から 遺言を見つけた場合 遺言の執行は相続人全員でするのが原則です。相続手続きは各種財産ごとに異なり、財産の種類によっては相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本などが必要になります。その都度、相続人全員の協力が必要となるととても手続きが大変です。相続人の間が仲がよく、また近隣に住んでいるならまだしも、相続人の間で疎遠になっている人がいる場合はなおさら手…
- 6. 遺言のトラブル&予防策を知る -遺言作成の準備の仕方 6 遺言のトラブル&予防策を知る遺言作成の準備の仕方 遺留分に気をつけること! 遺留分を無視した遺言はトラブルのもとです。遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産の割合で、被相続人が相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。被相続人が遺言により全財産を全く自由に処分できるとすると、相続人の間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤…
- 7. 任意後見契約公正証書 -遺言を書きましょう 7. 任意後見契約公正証書遺言を書きましょう 成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な者は、契約などの法律行為や財産管理を自分でおこなうことが難しい場合があります。判断能力の不十分な者を保護し、支援するのが成年後見制度です。後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の判断能力の程…
- 7. 遺言方式を知る -遺言作成の準備の仕方 7 遺言方式を知る遺言作成の準備の仕方 遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。それぞれに長所もあれば短所もありますので、十分に理解したうえで、選択することをお勧めします。 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言 利用できない人字の書けない人原則として誰でも利用可能※意思能力は必要字の…
- 8. いざ!遺言を書く -遺言作成の準備の仕方 8 いざ!遺言を書く遺言作成の準備の仕方 共同遺言の禁止 2人以上の者が同一の証書を用いて遺言をすることを共同遺言といい、共同遺言は民法975条によって禁止されています。その理由としては、1. 各遺言者の意思が相互に制約され遺言自由の確保が困難であること、2. 遺言者の一方が死亡した場合に他方がもはや遺言を撤回できなくなるため遺言撤回の自由を妨げること、3. 遺言の効力発…
- 9. 遺言を保管する -遺言作成の準備の仕方 9 遺言を保管する遺言作成の準備の仕方 保管場所は慎重に決める! せっかく書いた遺言書も発見されなければ無意味です。自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成した場合、遺言書を自分で保管しておく必要があります。遺言書は発見されやすいところに置くと見つけられて偽造・変造・隠匿される危険がありますので他人の目に触れないところに保管をする必要があります。しかしあまりにも発見されにくいとこ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
| 内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) | ||
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。