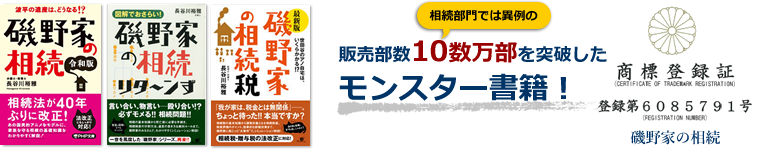相続放棄 -相続の放棄と承認遺産分割の弁護士
相続放棄相続の放棄と承認
相続放棄とは、被相続人の一切の財産を相続することを放棄することをいいます。相続放棄は、相続の開始によって相続人に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示を意味します。つまり、相続放棄によって初めから相続人ではなかったことになります。
なお、相続放棄は生前にはできません。例えば生前に相続放棄をしていても、相続開始後(被相続人が亡くなった後)に相続人としての権利を主張することは可能です。
相続放棄手続きは、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対する申述という方式によって行います。この手続によらなければ、相続放棄は法的な効果が生じません。
例えば、被相続人が多額の借金を残して死亡した場合、相続人が何の手続も行わず3か月が経過してしまうと、相続を承認したことになります。被相続人の債務の一切を引き継ぐことになりますので、債務を負いたくないのであれば、必ず裁判所による相続放棄の手続を行う必要があります。
なお、相続放棄の手続をする前後に、財産の全部または一部を使ったり隠したり財産の処分を行うと、法定単純承認をしたことになり、自動的に承認をしたことになってしまいます。相続放棄の権利を主張するには遺産には手を付けないことが重要です。
熟慮期間を経過している場合であっても、被相続人に負債がないと信じていたような場合には、相続放棄の申述は広く認められる傾向にあり、判例上も一定の要件のもと、そのような場合における相続放棄の有効性を認めています。借金を知らなかった事情を詳しく書いて、家庭裁判所へ相続放棄申述をしましょう。
ただし、家庭裁判所で相続放棄の申述書が受理されたとしても、債権者が訴訟を提起すると、その相続放棄が認められない場合もありますので、熟慮期間経過後の相続放棄の申述の際は弁護士などの法律専門家に前もって相談されることをお勧めします。
相続放棄と相続人
相続放棄をすることにより、当該相続人は、初めから相続人でなかったとみなされます。また相続放棄は、代襲相続の原因にはなりません。つまり、放棄した相続人によっては後順位の相続人に相続権が発生し、相続人の組み合わせが異なる場合がありますので注意が必要です。
例えば、 相続人が配偶者A、子(長男B・二男C・長女D)、被相続人の父母も兄弟姉妹(兄・妹)も健在の場合
子B・C・D全員が配偶者Aに全額を相続させたいと考え、相続放棄をしたとしますと、子B・C・Dは最初から相続人ではなかったことになりますので、相続人は配偶者と第2順位の相続人である父母(直系尊属)が相続人になります(ケース(2))。つまり、このケースでは、子が相続放棄したとしても母が全額相続できるわけではありません。
配偶者Aに全財産を相続させるには、相続人全員(もしくは子のうちの1人以上)が相続の承認をした上で、遺産分割協議書で配偶者が全財産を相続する旨の遺産分割協議を成立させる必要があります。相続財産を受け取らないことと相続自体を放棄することは異なるので注意しましょう。
被相続人に多額の借金があるため相続放棄をしようと考え、配偶者A、子B・C・D全員で相続放棄をしますと、配偶者も子らも最初から相続人でなかったことになるため、第2順位の相続人である父母(直系尊属)が相続人となります(ケース(4))。この場合、父母も相続放棄をしない限り、借金を負うことになります。放棄をする場合は、(相続放棄をしたことにより)自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に手続が必要です。
この父母の相続放棄が認められると、次に第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となります(ケース(5))兄弟姉妹も同様に相続放棄をすると、誰も相続しなかったことになりますので、債権者は誰にも請求できなくなります。
ただし相続人が保証人になっていた場合などには当然支払義務は残ります。
| 法定相続人が、配偶者B、子(長男A・二男B・長女C)の場合 ※第2順位の父母も第3順位の兄弟姉妹(兄・妹)もいる場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放棄手続きを行った相続人 | 相続人と法定相続分 | 備考 | ||
| (1) | 通常の場合 | 配偶者 | 1/2 | |
| 長 男 | 1/6 | 1/2×1/3 | ||
| 二 男 | 1/6 | 1/2×1/3 | ||
| 長 女 | 1/6 | 1/2×1/3 | ||
| (2) | 子の全員が相続放棄 | 配偶者 | 2/3 | |
| 父 | 1/6 | 1/3×1/2 | ||
| 母 | 1/6 | 1/3×1/2 | ||
| (3) | 子の1人(長女)が 相続放棄 | 配偶者 | 1/2 | |
| 長 男 | 1/4 | 1/2×1/2 | ||
| 二 男 | 1/4 | 1/2×1/2 | ||
| (4) | 配偶者と子の 全員が相続放棄 | 父 | 1/2 | |
| 母 | 1/2 | |||
| (5) | 配偶者と子全員 父母が相続放棄 | 兄 | 1/2 | |
| 妹 | 1/2 | |||
相続放棄の手続
相続放棄の申述は自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対して行わなくてはなりません。相続放棄を行う場合、共同相続人の了承など必要なく各相続人の意思で行うことができます。なお、この手続きによらなければ法的な効果が生じませんし、相続開始前に相続放棄手続きを行うことはできません。
相続放棄を申述する相続人が未成年者の場合は、父母が法定代理人として放棄の手続きを行いますが、その未成年者と法定代理人が利益相反関係にある場合は、未成年者のために別に特別代理人を選任して申述する必要があります。
相続放棄申述
相続放棄の申述書| 申 立 人 | 相続人・包括受遺者 |
|---|---|
| 申 立 先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立時期 | 相続の開始を知ったときから3か月以内 |
| 申立費用 | 収入印紙800円 予納郵券(郵便切手) |
| 添付資料 | ・被相続人の除籍(戸籍)謄本 住民票の除票 ・申述人の戸籍謄本 |
※必要書類、郵券につきましては裁判所によって異なる場合がありますので、申立て前に必ず家庭裁判所に問い合わせてから行いましょう。
手続きの流れ
- (1)申立書、添付資料および申立費用を家庭裁判所に提出して申述手続きを行います。
- (2)家庭裁判所から申立人宛に相続放棄の申述についての照会書が送付されます。照会書は、相続放棄の理由や財産の処分の有無など、本人の放棄の意思を確認をするものです。
- (3)照会書についての回答書を家庭裁判所に提出します。
- (4)家庭裁判所で当該申述につき審査され、特に問題がなければ相続放棄が正式に受理されます。
被相続人の債権者から請求が来た場合は、相続放棄受理通知書をもって支払いを拒否することができます。ただし、相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合などには当然支払義務は残りますので注意しましょう。
事実上の相続放棄
事実上の相続放棄とは、相続放棄の手続きをするべき熟慮期間が経過した場合や、家庭裁判所に対する申述のわずらわしさを避ける場合に、法的な手続きを行わずに、相続財産の取得を放棄したのと同じ効果をねらうものです。
具体的には、遺産分割協議に加わっても相続する財産をゼロとする方法や生前に特別受益としての贈与を受けているため相続分がない旨を証明する書面(「相続分皆無証明書」など)を作成する方法などがあります。
上記の方法は、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要なことなどの理由から、相続放棄に代わる簡易な方法として利用されています。ただし、「相続分皆無証明書」による相続放棄等は、あくまでも事実上の放棄であって、正式な相続放棄にはあたりません。法律上は相続を承認していることになりますので、例えば、相続財産に借金などがある場合は、債権者から弁済を請求されれば、債務の法定相続分を負担する義務が生じます。
事実上の放棄は実務上多く行われているのが現実です。ただし、財産を独り占めしようとしている相続人が、遺産の内容も知らない共同相続人に対していきなり「相続分皆無証明」を記載した文書を送り、これに署名・押印するよう求めるケースなど、トラブルも多いようです。安易な判断で「相続分皆無証明書」に印鑑を押すことはお勧めできません。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
『 遺産分割の弁護士 』のその他の記事
- 遺言による遺産分割
- 遺言による遺産分割遺産分割の方法 1 遺言は遺産分割に優先 2 遺言の種類と調査方法 3 遺言の検認手続 4 遺言の有効性を争う場合 5 遺言による遺産分割についての問題 遺言は遺産分割に優先 被相続人の遺言が見つかった場合は、遺言が遺産分割協議に優先します。遺言によって、法定相続分とは異なった相続分の指定をすることができますし…
- 遺産分割対象にならない場合がある財産 -相続財産の確定
- 遺産分割対象にならない場合がある財産相続財産の確定 株式 ゴルフ会員権 生命保険死亡退職金形見分けの品 生前贈与 株式 株式は必ずしも遺産分割協議の対象にはなりません。 株式も預貯金債権と同様、相続分に応じて分割され、必ずしも遺産分割協議の対象にはなりませんが、預貯金債権と同様に一般的には遺産分割協議の中で分割されます。 株式の評価 株式のうち上場株は、取引相場がありますので、客…
- 遺産分割の対象にならない財産 -相続財産の確定
- 遺産分割の対象にならない財産相続財産の確定 年金受給権 公営住宅の使用権 墓地などの祭祀承継 年金受給権 年金受給権は遺産分割の対象となりません。 被相続人が掛け金または保険料を負担した後に被相続人が死亡し、相続後にその遺族が年金の支払いを受けることがありますが、それが公的年金であっても、私的年金であっても、その受給権は遺族が原始的に取得するものであって、遺産分割の対象に…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
| 内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) | ||
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。