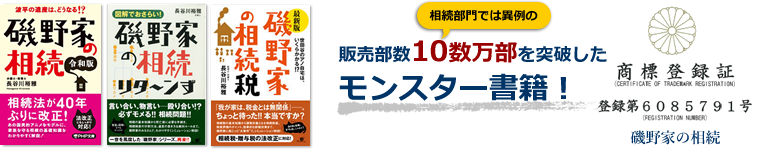1. 相続財産について知る -遺言作成の準備の仕方遺言の弁護士
- [CATEGORY]:
- 知識の解説 遺言作成の準備の仕方
- [TAG]:遺言,遺言作成
1 自分の財産について知る遺言作成の準備の仕方
財産リストを作成する
まず自分の財産について整理し、財産リストを作成しましょう。家族であってもあなたの財産について、知らないということはよくあることです。もしかするとあなた自身も把握できていない財産があるかもしれません。相続リストがないと、相続開始後に相続人が調査によって調べることになります。それでは相続人に時間も労力も費用も使わせてしまうことになりますし、もしかしたら、見つけだすことができない財産もあるかもしれません。財産について一番知っているはずのあなたが相続リストを作っておくことで相続人の負担を軽くしてあげることができます。
財産リストを作成し、今あなたがどんな財産を持っているかが明らかになれば、誰に何を残したいかも明確に考えることができます。遺言を作成することまで考えていない人でも、相続リストだけでも作成しておけば、相続人が遺産分割を行う際に、遺産を見つけだす手間が省けますので、相続人の負担を避けることもできます。
さっそく、財産リストを参照に自分の財産を整理してみましょう!!!
相続財産には預貯金、不動産、株券、装飾品などさまざまなものが考えられます。これらの財産について、例えば預貯金がどこの金融機関にどれだけあるか、どこにある不動産なのかまで詳細に書いておきましょう。不動産の詳細については不動産登記簿謄本を取り寄せれば正確な情報がわかります。あなたが以前に相続した不動産でまだ名義変更をなされていないものがある場合はこの機会に名義変更を行っておくことをお勧めします。
相続財産には不動産や預貯金のような正の財産だけでなく、借金や借入金などの負の財産も含まれます。例えばあなたが誰かの連帯保証人になっている場合は、その地位も相続人に引き継がれることになりますので、忘れずに記載しておきましょう。
相続財産について
預貯金
預貯金は相続の対象になります。相続人は名義変更や払い戻し請求をして預貯金を承継します。遺言の中に、預貯金を特定して、特定の相続人に「相続させる」旨の指定がない場合は、預貯金の名義変更や払い戻しの請求の際に、銀行から遺言書もしくは遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明と住民票、戸籍謄本、除籍謄本などの必要書類を要求されることがあります。
不動産
相続財産の中で不動産は大きな割合を占めることが多いようです。不動産は共同相続人間で分けることが難しく、分割で価値が下がることもあるので、相続争いの中心課題になることも多いといわれます。特に相続財産が不動産しかない場合に、数人の相続人のうちの1人が遺言で不動産を相続することになると、他の相続人の相続分がなくなります。主たる遺産が不動産で、それを現物分割するのが困難である場合にとられる分割方法として、換価分割(不動産を未分割の状態(共有)で遺産を売却処分してその売却代金を共同相続人間で分割処分する方法)、代償分割(特定の相続人が不動産を取得し、その代わりにその者がほかの相続人に対して代償金を支払う方法)があります。
借地権・借家権
借地権、借家権は財産上の権利として相続の対象になります。借地上の建物や借家に住んでいる相続人は借地権や借家権の名義人が亡くなった場合でも、借地契約・借家契約をそのまま相続します。被相続人と同居していなかった相続人でも、権利があります。
借地権や借家権に関しては、内縁の妻が問題になることがあります。内縁の妻は相続人にはならないのですが、居住用の借家権に関しては、相続人がいない場合に限り内縁の妻でも借地借家法の規定によって借家権を承継することはできます。ただし、相続人がいて借家権を主張してきた場合には、適用されませんので話し合いになります。
借地上の建物を生前贈与や遺贈によって内縁の妻名義にし、借地権を相続するのと同じ効果を期待することができます。地主に対しては、念のために名義変更料を払って名義変更を承諾してもらうと万全です。
損害賠償請求権
被相続人の有体財産についての損害賠償請求権は、財産上の権利であり、相続の対象になります。
事業資産
株式会社や有限会社については、株式会社の場合は株式の相続、有限会社の場合は出資の持分の相続になります。会社の相続の場合は株式の名義を書き換えるだけで、会社所有の不動産などの名義をいちいち個別に書き替える必要はないので、会社組織であれば相続を簡便に行うことができ、事業の断絶が起こりにくくなります。
個人企業の相続は一般の相続と同じで、特許権や実用新案権、意匠権、商標権、電話加入権、不動産、借地権・借家権、自動車、機械設備、動産、債権、債務など相続財産ごとに個別の手続きが必要です。商売上ののれんが相続財産になることもあります。
借 金
被相続人が銀行の債務を負っていたり、連帯保証人になっていたりして、債務がある場合も、相続人に相続されます。債務が過大であるときは相続人は相続放棄ができます。相続人の1人が相続放棄すると、残りの相続人がその分を負担します。相続放棄をしない場合には、法定相続分に沿った債務を負います。
なお、保証債務であっても、身元保証や責任限度額や保証期間を定めずに連帯保証人になっていた場合などは、被相続人の一身専属的なもので相続されません。
生命保険金
保険金請求権は相続財産ではなく、受取人として指定された者の固有の権利です。保険金受取人として請求権発生当時の相続人を指定した場合には、保険金請求権は保険契約の効力発生と同時に指定された相続人の固有財産となります。生命保険金の受取人が「法定相続人」などと指定されている場合には、保険金請求権発生当時の相続人が、法定相続分に従って保険金請求権を原始的に取得することになります。保険金請求権は相続財産ではないので、相続放棄をしていても受け取ることができますし、保険金を受け取ったとしても相続放棄ができます。
公営住宅の使用権
公営住宅の使用権は通常の賃借権と異なり、公営住宅は入居者の入居資格を審査したうえで、その者の生活のために入居を認めるもので、当然に相続するものではありません。相続人が再度、入居資格を審査されて、条件を満たせば引き続き居住することができます。
墓地などの祭祀承継
系譜、祭具、墳墓などの祭祀は祭祀財産といい、相続財産には含まれません。
被相続人の生前の指定か遺言で指定された者か、指定がない場合は慣習に従い、どちらもない場合は家庭裁判所に調停または審判を申し立てて決めます。祭祀財産を継承しても法律上は、相続財産の増減にはつながりません。被相続人が祭祀継承者の指定と合わせて祭祀費用相当額の遺贈をすることもできます。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺言のことなら『遺言の弁護士.com』
だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。
- 2019-08-19
- [CATEGORY]: 知識の解説,遺言作成の準備の仕方
- [TAG]:遺言,遺言作成
『 遺言の弁護士 』のその他の記事
- 知識の解説
- 遺言トラブルのポイントや遺言に関する法律用語の解説を紹介しています。 遺言を書く 遺言を残すべき人や遺言を書くタイミング、遺言の文例や遺言に類似した制度など、遺言作成を始めるにあたって知っておきたいポイント 1. 遺言を書きましょう2. 遺言を残すべき人3. 遺言を書くタイミング4. 遺言執行者とは5. 遺言の文例6. 死因贈与契約7. 任意後見契約公正証書 遺…
- 遺言がみつかったら(検認手続など) -よくある質問 遺言Q&A
- 遺言がみつかったら(検認手続など)よくある質問 遺言Q&A 検認手続は必要ですか? 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は検認手続が必要ですが、公正証書遺言の場合は不要です。検認手続とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言の内容を明確にして、遺言の偽造、変造を防ぐ手続きです。遺言の内容を実現するには検認手続が不可欠で、例えば、検認手続を経ていない自筆証書遺言に基づいて不動産の登記をしようとして…
- 遺言作成にあたっての注意点 -よくある質問 遺言Q&A
- 遺言作成にあたっての注意点よくある質問 遺言Q&A 未成年は遺言をすることはできますか? 満15歳に達していれば遺言をすることができます。ただし、満15歳に達した人でも、意思能力のない人は遺言をすることができません。遺言能力のない人のした遺言は無効です。遺言能力とは、遺言をするのに必要な意思能力をいいます。 成年被後見人は遺言をすることができますか? 成年被後見人でも遺言ができる場合があります。成年被後見人とは、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
| 内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
| 来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
|---|---|---|---|
| 内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
| 対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
| 調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
| 弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
| その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
| 税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
| 国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) | ||
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。